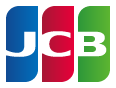開業・出店
【飲食店開業まとめ】開業までの流れや必要な資格など準備段階の疑問を解決!
更新日:2024年1月31日

これから飲食店を開業しようとする場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか。必要な資格や、押さえるべきポイントなども知っておきたいところです。
この記事では、飲食店を開業する際の流れや開業前に押さえておきたいポイントなどについてわかりやすく解説しています。開業後にチェックしておきたい内容も網羅していますので、飲食店開業を検討中の方はもちろん、本格的に開業手続きを進める際の参考としても幅広く役立つ内容となっています。
この記事でわかること
- 飲食店を開業する際の大まかな流れ
- 開業準備をする際、特に押さえておきたいポイント
- 多様な決済方法への対応や、売上管理/経営分析の重要性
目次
JCB加盟店様限定
無料ダウンロード
有料サービスの「JCB消費NOW」で提供している個人消費動向レポートを、限定公開中!店舗の売上見通しや戦略策定にお役立ていただけます。
- ※2023年11月現在最新版

資料DLはこちら
1 飲食店開業までの流れ

飲食店を開業するまでの大まかな流れは、概ね次のようになります。
1-1 コンセプト決定、事業計画書の作成
飲食店開業においては、まずコンセプトをしっかりと固めることが重要です。コンセプトとは「構想」「考え」といった意味で、どのようなお店にしたいかというイメージのことです。お店のコンセプトを決める際には、5W2Hのフレームワークを活用すると明確になります。5W2Hとは「いつ(when)」「どこで(where)」「誰に(who)」「何を(what)」「なぜ(why)」「どのように(how)」「いくらで(how much)」の頭文字を取ったもので、情報を整理したり、分析して他者へ伝えたりするのに役立ちます。
| 5W2Hを使った飲食店の基本コンセプト例(順不同) | |
|---|---|
| 何を(what) | 10坪程度、創作ラーメンの路面店 |
| 誰に(who) | 20~40代のビジネスパーソンがメインターゲット |
| どこで(where) | 〇駅周辺、〇〇エリアなど |
| なぜ(why) | 競合が少ないオフィス街で独自性のあるラーメンランチの提供で集客を狙う |
| いつ(when) | 〇ヵ月後、〇月〇日など(目標とする開業日) |
| どのように(how) | 上品な洋風ラーメンとピラフのセット、焼きそば弁当など |
| いくらで(how much) | 単品980円、ランチセット1,000~1,800円、弁当680円など |
飲食店の種類とターゲット、出店したいエリアやお店の大きさ、メニュー開発にまで、コンセプトが深く関わってきます。「何を、誰に」のコンセプトによって「どこで、いくらで」が変わってくる場合もあるでしょう。物件選びや内外装、価格や支払い方法を決める際にも、コンセプトに矛盾がないかを確認しながら決めることが大切です。
コンセプトが決まれば、事業計画書の作成もスムーズに進みます。事業計画書は、初期費用が足りない際に融資を受けたり、各種助成や補助を申請したりする際に必要となるものです。
事業計画書では、将来的に成功が期待できると納得させられる要素がどのくらいあるかが重要となります。提出先によっても異なりますが「なぜ開業するのか(why)」の部分に説得力があることや、運転資金を含む自己資金が一定以上あること、融資や助成を受けた場合の返済能力が充分であることなどがわかるように書かれているとよいでしょう。
1-2 物件選定、資格取得
また、飲食店開業に必要な資格も取得しておきます。飲食店開業に必要な資格としては
- 食品衛生責任者:飲食店開業に必須の資格
- 防火管理者:収容人数30名以上の店舗で必要となる資格
などが挙げられます。開業に必要な資格については、後述でさらに詳しく解説していきます。
1-3 開業届、営業許可申請
飲食店を開業する物件が決まったら、保健所へ営業許可の申請を行います。営業許可証を取得するには、申請後店舗への立ち会い検査を受ける必要があります。衛生的に営業するために必要な設備が整っているかといった点がチェックされるため、申請する前に管轄の保健所へ事前に相談してみましょう。はじめて開業する場合は、税務署へ開業届の提出も必要です。
1-4 内外装工事、備品購入、仕入
内装や外装工事は、以前のオーナーが飲食店として使用していた「居抜き物件」と、まったく設備のない「スケルトン物件」では、工事にかかる期間と費用が大きく異なります。特に厨房やお手洗いなど、水回りの設備は費用が大きくなりがちです。
家具や調理器具、カウンターテーブルなども、業務用や大型のものは新品で購入するとコストが大きくなりやすいでしょう。開業後に使用する食材や紙ナプキン、コースターなどの消耗品も準備が必要です。安定して仕入れができる業者も見つけておきましょう。
会計時の決済に関する整備も、開業前に進めておきましょう。券売機またはレジの購入に加え、近年ではクレジットやコード決済など、決済方法も多様化してきています。開業後の集客やリピート率を考慮するなら、決済方法の選択肢も広げておくとよいでしょう。
1-5 立会検査、許可証取得、開業
内装、外装工事などが完成し、保健所の立ち会い検査後に営業許可証を取得すれば、晴れて営業が可能となります。
2 飲食店開業時に押さえておきたいポイントをチェック!
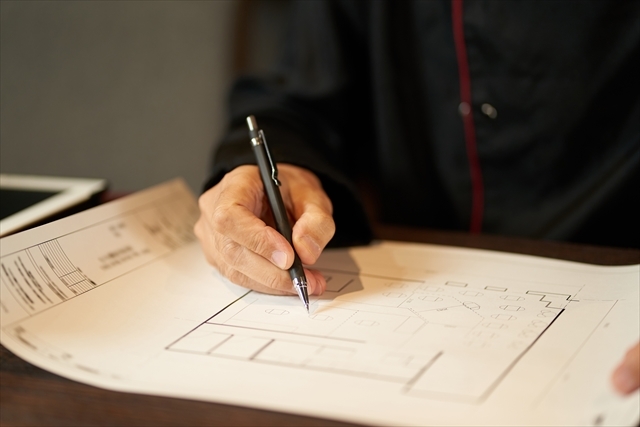
飲食店を開業する際に押さえておきたいポイントをピックアップして解説します。
2-1 コンセプト設定が重要
飲食店の開業において、コンセプト設定はとても重要です。どのエリアで物件を取得するか、営業時間やターゲットとなる顧客層が好みそうな価格帯、メニューなど、コンセプトによって店舗の方向性が決まることになります。
例えば「ファミリーや主婦層向けのカフェ」であれば、都市圏だけでなく郊外も物件探しのエリア範囲に入れられる場合があるでしょう。高価格帯のメニューを提供するレストランであれば、内装や食器、照明なども高級感を演出する必要があります。コンセプトから外れた店舗づくりをしてしまうとちぐはぐな印象を与えるだけでなく、集客にも影響が出てしまう可能性があるため注意しましょう。
2-2 開業までに必要な期間
どんなに早く開業したくても、コンセプトや事業計画書の作成、物件の選定など、開店準備には一定の期間が必要です。
規模や物件によっても異なるものの、少なくとも6ヵ月は見ておくようにしましょう。
2-3 開業時に必要な資格、届出
開業時に必要な資格として、食品衛生責任者と防火管理者の2点が挙げられますが、防火管理者は収容人数30名以上の場合に必要となるため、実質取得が必須となる資格は「食品衛生責任者」といえます。
食品衛生責任者の資格は、全国にある食品衛生協会(東京都の場合:一般社団法人東京都食品衛生協会)が主催する講習を受講することで取得が可能です。栄養士や調理師といった免許を取得している場合、講習を受講していなくても食品衛生責任者の資格があるとみなされます。
防火管理者の資格は、管轄の消防署(東京都の場合:東京消防庁)が主催する講習を受講することで取得が可能です。
飲食店の開業時に必要な届出としては、飲食店の営業許可が必須となるほか、防火や防災関連の届出を消防署へ行う必要があるケースもあります。工事業者が届出を行う場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
また、深夜にバー営業をする予定がある場合は、飲食店とは別に「深夜酒類提供飲食店」としての届出も必要となります。各地方自治体によって細かなルールが異なるため、不明な点は事前に管轄の保健所や消防署等へ確認することをおすすめします。
このほか、税務署への開業届や法人にする場合は登記手続きなども必要となります。
2-4 飲食店開業に必要な費用
飲食店開業時に必要な費用としては
- 物件を取得する費用
- 備品や設備を購入する費用
- 改装工事にかかる費用
- 仕入代
- 広告宣伝費(看板、のぼり、ポスター、チラシ、メニューなど)
などが挙げられます。開業時にかかる費用だけでなく、開業後しばらくは赤字でも営業を続けられる数ヵ月分の運転資金も準備するようにしましょう。
2-5 店舗物件を選ぶ際のポイント
店舗物件を選ぶ際、築の新しさや物件の広さ、立地などによっても取得費用は異なります。一般的には「広い」「築年数が新しい」「繁華街や駅から近い」「路面店」などの条件は、集客しやすいメリットがあるため、取得費用も高くなる傾向にあります。
逆に郊外にあるお店や小さなお店、地下や上階にある物件は集客の難しさがある反面、取得費用は安く抑えやすいでしょう。
また、居抜き物件は設備工事費用が抑えやすい分取得費用が高くなる場合があり、スケルトン物件は設備工事に費用がかかる反面、自分のこだわりを設備や内装に反映しやすいメリットもあります。すべての条件がよいと取得費用は高くなりがちなため、メリットとデメリットを比較しつつ優先順位を決めて選ぶことが大切です。
3 開業直前、開業後にチェックしたいポイント
開業する直前や開業後にチェックしたいポイントについても解説します。
3-1 DIYを活用する
広告宣伝には、費用のかからないSNSを最大限活用しましょう。また、外壁や内装など、自身の手でできるものは業者へ依頼せず自身で行うことで、初期費用を抑えることが可能です。オープン前からDIYの様子を撮影してSNSへ投稿するのもおすすめです。
3-2 多様化する決済方法に対応する
カード払いや電子決済など、多様な決済方法に幅広く対応できるようにしておくことも、集客の間口を広げるために重要なことの1つです。決済システムの導入には1~2ヵ月かかるケースが多いため、早めに手続きを済ませるようにします。開業までに間に合わない場合は「〇月〇日よりクレジット利用可能」など、レジ前に掲示しておくようにしましょう。
3-3 売上管理、経営分析も重要
客単価や原価率などの分析を行うことも、安定して経営を続ける為に重要です。とはいえ、開業後は忙しく「売上の集計や管理が難しい」「こまめに分析する時間がない」という悩みを抱える方も多いでしょう。
JCBグループでは、開業後の経営をサポートする次のようなサービスを提供しています。
『JMSおまかせサービス』
多様化する決済方法にスムーズに対応できるサービスです。1度の手続きでクレジットカードも電子マネーもまとめて利用可能にできるため、振り込みや問い合わせを一元化することができます。売上明細もウェブ上でかんたんに確認可能です。
『JMSおまかせサービス』の詳細はこちら
『tance mall』
POSレジやモバイルオーダーなど、店舗運営に役立つサービスを利用シーンに応じたデバイスで使えるプラットフォームで、店舗の困りごとをまるっと解決します。
『tance mall』の詳細はこちら
『JCB消費NOW』
JCBとビッグデータ解析ノウハウを持つ株式会社ナウキャストが開発したサービスです。業界の消費動向などについて、知りたい情報をわかりやすく分析することが可能です。
『JCB消費NOW』の詳細はこちら
4 まとめ
飲食店を開業する際には、コンセプトをしっかりと固めた上で、半年程度は期間に余裕を持ち、開業までの流れを把握してスムーズに進めることが大切です。開業後の経営を軌道に乗せるためにも、プロのノウハウやツールを活用しながら成功を目指しましょう。
- 記事の情報は当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その確実性を保証したものではありません。
- 記事は外部執筆者の方等にも制作いただいておりますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
- また、一部、当社または当社関係会社にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- なお、記事の内容は、予告なしに変更することがあります。