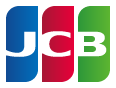年会費永年無料!
サービスも充実のJCBのスタンダードカード
クレジットカードを便利に活用する
サラリーマンができる節税対策とは?節税方法や注意点などのポイントをご紹介
公開日:2021年12月1日

手元にお金を少しでも多く残したいと、サラリーマンができる節税対策に興味のある方も多いのではないでしょうか。一般的な節税対策にはさまざまなものがありますが、サラリーマンの場合、所得税や住民税などの税金は給与から天引きされるため、まずは、自身がもらっている給与の内訳についてよく知ることも大切です。この記事では、サラリーマンの給与の内訳や節税の方法、注意するポイントなどについて紹介します。
サラリーマンの給与の内訳
サラリーマンが受け取る給与からは、税金や社会保険料などがあらかじめ差し引かれています。新入社員の頃、提示された給与額より受け取った額が少ないことに戸惑った方もいるのではないでしょうか。
給与明細に書かれた金額(額面)から税金などが引かれ、実際に手元に入る収入を手取り収入といいますが、自分の意思で使える所得という意味から「可処分所得」とも呼ばれます。手元に残るお金を増やすには、まず、自分の給与からどんな項目が天引きされているのかを知り、最終的に手元に入る可処分所得を増やしていく意識を持ちましょう。
給与から差し引かれる税金と社会保険料の種類は以下の通りです。
<税金>
・所得税
所得税は累進課税制度が導入されています。税率は以下の通りです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
(2021年12月現在)
・住民税
定額で課税される「均等割」と前年の所得金額に課税される「所得割」を合計した金額を支払います。所得割の税率は10%(2021年12月現在)です。
<社会保険料>
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 介護保険料
なお、サラリーマンなどの給与所得者には「年末調整」の制度があります。これは、12月にその年の給与総額が決まるため、月々天引きされている所得税を再計算して、払い過ぎがあれば戻し、足りない分があれば再徴収するためです。この際、配偶者控除や扶養控除ほか、生命保険や地震保険、住宅ローン控除など、個人によって異なる控除額の計算も行われるため、節税につながる控除項目がないか、よく確認する必要があります。次では、年末調整で受けられる控除、受けられない控除などについて詳しく紹介します。
サラリーマンができる節税対策と注意するポイント
サラリーマンができる節税対策として、年末調整に注目して解説します。
年末調整で受けられる控除
会社で年末調整を行う際に受けられる控除がいくつかあります。控除を受けるとその分、税金額を低くできるため、節税につながります。ただし、制度の内容が頻繁に見直されるなど、想定通りに控除が受けられないこともあり、注意が必要です。
勤務先の年末調整で受けられる控除は以下の通りです。
<扶養控除>
・扶養控除
子どもや両親など、親族を養っている方が受けられる控除です。扶養控除の金額は、年齢や同居の有無によって異なります。
| 扶養親族の年齢 | 扶養控除額 |
|---|---|
| 満15歳以下(年少扶養親族) | 0円 |
| 16歳以上 18歳以下(一般扶養親族) | 38万円 |
| 19歳以上 22歳以下(特定扶養親族) | 63万円 |
| 23歳以上 69歳以下(成年扶養親族) | 38万円 |
| 同居かつ70歳以上(老人扶養親族) | 58万円 |
| 同居以外かつ70歳以上(老人扶養親族) | 48万円 |
(2021年12月現在)
・障害者控除
自分や同一生計の方が障害者である場合に受けられる控除です。各種機関で障害者手帳を交付された方が対象となります。障害者控除は障害の程度によって判定が異なり、より重い障害を持っていることを示す「特別障害者」と認められれば、控除額も大きくなります。
・勤労学生控除
特定の学校に通いながら就労する場合に受けられる控除です。
・寡婦控除
夫と離婚または死別して再婚していない女性が受けられる控除です。
・ひとり親控除
シングルマザー、シングルファーザーの方が受けられる控除で、男女問わずに受けられます。
<配偶者控除>
・配偶者控除
配偶者がいる方が受けられる控除です。
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
|---|---|---|
| 一般控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (12月31日時点で年齢が70歳以上の人) |
|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(2021年12月現在)
・配偶者特別控除
配偶者控除の対象とならない場合でも、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。
| 配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
| 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
(2021年12月現在)
<保険料控除>
・社会保険料控除
自分や同一生計である配偶者、親族が社会保険料を支払っている場合に受けられる控除です。支払額の全額が所得から控除されます。
・小規模企業共済等掛金控除
共済制度の掛金を支払っている方が受けられる控除です。支払っている場合はその全額が所得から控除されます。
・生命保険料控除
一般生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている方が受けられる控除です。控除される額は契約したタイミング(平成24年1月1日以後に締結または平成23年12月31日以前に締結)によって異なります。
・地震保険料控除
地震保険料または平成18年末までに契約した満期返戻金のある契約期間10年以上の旧長期損害保険を支払っている方が受けられる控除です。
<その他>
・所得金額調整控除
年収850万円を超えていて、(1)本人が特別障害者、(2)23歳未満の扶養親族がいる、(3)特別障害者である配偶者または扶養親族がいる、のいずれかに該当する場合に受けられる控除です。
・基礎控除
合計所得金額に応じて受けられる控除です。例えば、合計所得金額が2,400万円以下の場合の控除額は48万円です。
・住宅借入金等特別控除
住宅ローンを利用してマイホームを新築、取得、増改築などをした場合で、一定の条件を満たすときに受けられる控除です。「住宅ローン控除」とも呼ばれています。なお、適用初年度は確定申告が必要なため、注意が必要です。
年末調整以外で受けられる控除
年末調整以外にも節税対策として受けられる控除があります。
・寄附金控除(ふるさと納税など)
特定団体に寄付した場合に、所得税や住民税を控除できる制度です。代表例に「ふるさと納税」が挙げられます。ふるさと納税は所得で控除限度額が決まるため、事前確認が必須です。
・医療費控除
自分や家族の医療費(妊娠・出産にかかる医療費含む)で10万円を超える額を支払ったときに受けられる控除です。
・雑損控除(自然災害や盗難等で被害を受けた)
自然災害や火災、盗難、横領などで被害を受けた方に適用される控除です。
副業をしている方は、副業に関する節税対策も知りたいところでしょう。副業での所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。副業を本業にしたいと考えている方(継続的な所得が見込める方)は、開業届と青色申告承認申請書を提出しておきましょう。副業の所得を事業所得として確定申告すると、最高65万円の特別控除が受けられます。副業で使用した交際費や家賃、光熱費の一部も経費として扱うことができるため節税できます。副業で自宅を利用している場合は、利用スペースや時間を公私で分けて経費計算しましょう。
なお、開業届を出すとよいことだらけに思えますが、注意点もあります。サラリーマンで開業届を提出すると、失業手当が受給できません。法人化したい場合は、会社設立費用や決算処理、赤字でも税金を支払えるのかなど、さまざまな事項を慎重に検討する必要があります。
また、副業を行っていない場合でも、年収2,000万円以上の方は年末調整の対象外とならないため、確定申告が必要です。
各種税金はクレジットカード支払いで節税
会社員の場合、所得税や住民税などは給与から天引きされますが、固定資産税や自動車税など個人で支払う税金はクレジットカードでの支払いが可能な場合があります。クレジットカードでの支払いは、時間や場所を問わずにできる、支払い回数を分けたり、手元に現金がなくても支払える、利用履歴の管理が簡単などのメリットがあります。また、クレジットカードで支払うことで多少の手数料がかかる場合もありますが、ポイントの還元を受けることができるため、実質的に税額を抑えることにつながります。
各種お支払いでポイントも貯まり便利なサービス満載のJCBカード
税金や普段の買い物をクレジットカード払いにすることでポイントが貯まり、現金で支払うよりおトクです。副業をしている方は、経費をクレジットカード払いにすることで利用明細がわかりやすくなり、管理しやすくなります。今回は、クレジットカードのなかでもおすすめのJCBカードについて紹介します。
JCB カード S

年会費無料で優待も充実している「JCB カード S」が新登場!
JCB カード Sは、18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上の方が申し込みできます。
年会費は永年無料なので、初めてのクレジットカードや2枚目のクレジットカードにおすすめです。
JCB カード Sは年会費が無料なうえに、充実した優待サービスがついています。「JCB カード S 優待 クラブオフ」は、国内外20万ヵ所で利用できる割引優待サービスです。グルメ、レジャー、映画館やカラオケなどのエンタメ、ホテル、テーマパークなどで割引を受けることができます。
他にも、パートナー店での最大20倍のポイントアップ、旅行傷害保険やJCBスマートフォン保険をはじめとした各種保険も付帯しています。
いまなら新規入会限定のおトクなキャンペーンも実施中!
JCB カード W
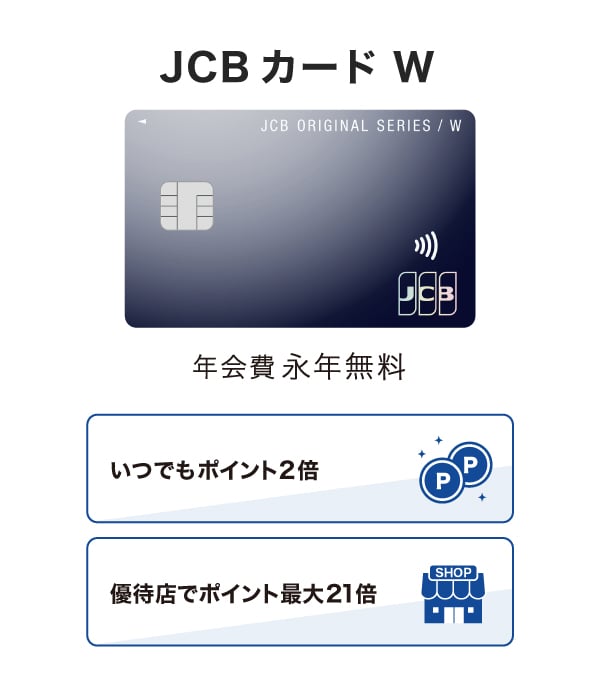
JCB カード Wは高校生を除く18~39歳限定で申し込める、年会費が永年無料のクレジットカードです。39歳までに入会しておけば、40歳以降も年会費が永年無料で利用できます。コストを抑えておトクにクレジットカードを利用したい方にぴったりです。
JCB カード Wは、JCBカードのなかでも特にポイント還元率が高いのが特徴です。国内・海外のどこで利用しても、Oki Dokiポイントが2倍たまります。JCBオリジナルシリーズパートナーで利用すればさらにポイントが高還元になり、おトクに買い物ができます。

- 1 Starbucks eGiftの購入は21倍、スターバックス カードへのオンライン入金・オートチャージは11倍です。店舗での利用分・入金分はポイント倍付の対象となりません。
- 2 Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
- 3 一部対象とならない店舗があります。法人会員の方は対象となりません。日本国内に限ります。
- JCB カード Wを利用するとカード特典の+1倍が加わるため、上に記載のポイント倍率が適用されます。
- 掲載内容は予告なく変更となる場合があります。
ポイント倍率は2024年4月時点の情報です。
事前にポイントアップ登録が必要です。優待店により特典・条件等が異なります。最新情報はJCBオリジナルシリーズサイトをご確認ください。
たまったポイントは他社ポイントやマイルに移行できるほか、1ポイント3円でキャッシュバックも可能です。Amazon.co.jpでの買い物では、ポイントの移行手続きをすることなく、1ポイント3.5円分で利用できます。
- ポイント移行商品などの申し込み可能ポイントは商品により異なります。
JCB カード W plus L

JCB カード W plus Lは、「JCB カード W」に加え、女性特有の疾病をサポートする「女性疾病保険」や、ホテルやコスメなどの優待・特典を受けられる「LINDA リーグ」サービスがついています。
申し込みは18~39歳限定で、性別は問いません。40歳以上になっても年会費無料で利用できます。
女性疾病保険は、通常の疾病に加えて女性特有の疾病による入院・手術費用がサポートされます。リーズナブルな料金で加入できるのがメリットです。
LINDAリーグの優待情報は毎月変わります。ホテルやグルメ、エンタメ施設を優待価格で利用できるほか、キレイを応援するアイテムのプレゼントなどさまざまです。こまめにチェックして、積極的に活用しましょう。
詳しくは、JCB公式のInstagramやWEBサイトを確認してください。SJ23-09688(20231107)
【JCB公式】LINDAサービスのInstagramはこちら
JCBゴールド

JCBゴールドは、JCBブランドの安心感・信頼感に加えてステータスの高さが魅力のゴールドカードです。WEB明細サービス「MyJチェック」に登録し海外利用をすると還元率が2倍になるほか、国内外の旅行傷害保険が充実しています。また、国内の主要空港、およびハワイ ホノルルのラウンジを無料で利用できるなど、国内旅行や出張が多い方に最適です。
またJCBゴールドを保持していれば、一定条件を満たした方限定でワンランク上のサービスが受けられる「JCBゴールド ザ・プレミア」への招待が届きます。クレジットカードを育てて、今後さらにステータスの高いカードを持ちたい方にもおすすめです。
まとめ
サラリーマンができる節税対策にはさまざまなものがありますが、それぞれのメリットや注意するポイントなども押えながら自分に合った節税対策を行いましょう。
副業や各種税金については以下の記事も参考にしてください。
関連リンク
お金は管理して貯めるが鉄則! お金が貯まらない要因と貯めるために実践したい行動とは
住民税はクレジットカードで支払える?メリット・デメリットを紹介
自動車税をクレジットカードで支払うのはおトク?メリットや注意点を詳しく解説
固定資産税をクレジットカード払いする方法|手数料や注意点を解説
注意事項
本ページ記載の内容は2021年12月現在のものです。
また記載内容は予告なく変更となる場合があります。
この記事に関連するカード
ゴールドカードならではの安心とクオリティーを兼ね備えた1枚
ポイント還元率が高い年会費無料のクレジットカード
ポイント還元率が高い年会費無料のクレジットカード